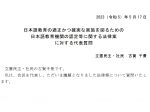日本語教育は「国の責任で」 推進基本法案の原案を提示 日本語議連の総会で
- 2018/5/29
- 日本語議連
- 日本語教育推進基本法, 日本語教育推進議員連盟
- 889 comments

日本語教育は「国の責任で」 推進基本法案の原案を提示 日本語議連の総会で

[第10回総会であいさつをする河村健夫会長]
超党派の日本語教育推進議員連盟(河村建夫会長、略称・日本語議連)は5月29日午前、参院議員会館で第10回総会を開き、日本語教育推進基本法(仮称)の政策要綱を了承した。日本語議連は各党の了承を得たうえで条文化作業を行い、早ければ秋の臨時国会に提案する意向だ。要綱では、日本語教育を「喫緊の課題」だとし、推進政策の策定、実施を国と地方自治体の「責務」として位置づけている。外国人が急増する中、基本法が成立すれば国と地方自治体の責任において日本語教育の推進事業が行われることなる。
要綱は、「総則」「基本方針等」「基本的施策」「日本語教育推進協議会等」「その他」の5つの章で構成。総則の基本理念では、国籍、年齢を問わず「希望する全てのもの」に日本語教育を受ける機会が確保されなければならないとし、その推進にあたっては、関係省庁が有機的に連携し、総合的に行われなければならないと明示した。
国の責務については、「国は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること」と記述。また、地方自治体についても、地方の状況に応じた施策を実施するよう「責務」を課した。そのうえで施策を推進するための基本方針を、政府に対しては「定めなければならない」とし、地方自治体には策定の努力を促した。

[日本語教育推進基本法(仮称)政策要綱について説明をする衆議院法制局の津田樹見宗課長]
基本的施策の中には、外国人の児童生徒、留学生、就労者・技能実習生、難民に対する日本語教育について「必要な施策を講ずる」よう国に求め、地域の日本語教室などの支援や共生社会の実現に資するよう日本語教育への国民の理解を深めることも求めた。日本語指導が必要な外国人児童は3万4000人にのぼり、地域によっては学校現場で大きな課題となっており、その対策が急がれる。
一方、海外における日本語教育の普及促進については、現地における日本語教育の体制・地盤の整備の支援、日本語教育人材の育成、教材の開発、提供(インターネットを通じたものを含む)などの「必要な措置を講じるよう努める」-―ことなどを記した。
また、日本語教育の質の保証については、先の文化審議会国語分科会の提言を受けて文化庁が日本語教師の養成・研修の在り方に関する指針を改定したが、要綱では日本語教師の「待遇の改善」や「資格」についても「必要な施策を講ずるものとする」とした。
さらに「国の責務」を遂行するのにあたり、政府内で関係府省の調整を図るため「日本語教育推進協議会」と、協議会に意見具申する、有識者による「日本語教育推進専門家会議」の設置を求めている。これからの機関は施策を具体的に進めるための重要な役割を果たすことになる。
留学生の日本語教育の最前線にある日本語学校の「制度の整備」について、要綱には「検討を加え、教育の水準の向上を図るため、必要な施策を講じるものとする」と検討条項として盛り込んだ。日本語学校は専門学校、各種学校、株式会社など形態が多様であるほか、業界団体が複数あるなど、日本語議連はその在り方を基本法に直接規定するのは難しいと判断したようだ。国は日本語学校に関する制度上の課題などを精査し、学校現場の関係者から事情を聞くなどして対策を検討するものとみられる。
総会では、要綱の内容を支持し、法案の早期成立を求める意見が相次いだ。要綱の今後の扱いは河村会長に一任され、日本語議連としては各党の了解を得たうえで、衆院法制局の協力を得ながら条文化に着手。条文化作業には1か月余りかかるとみられる。このため基本法案は早ければ秋の臨時国会、場合によっては来年の通常国会での成立が見込まれる。
総会の閉会にあたり河村会長は「今回は大方針をたて、日本語教育は国が責任を持つようになる。外国人を受け入れる企業、地方自治体も国の方針に従って教育を進める形をとることが基本になっている。それを中心になって進める省庁がどこであるかも明確にしていかなければならないと思っている。まだまだ詰めなければならない点もあると思う。日本語を教える先生の質とか、いろいろ問われてくる。そうしたことに対しても国が責任を持つということがこの議員立法の趣旨だ」と述べた。
日本語議連の総会で了承された「日本語教育推進基本法案(仮称)政策要綱」の全文は以下の通り。
日本語教育推進基本法案(仮称)政策要綱 [PDF表示]