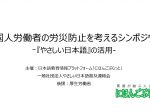- Home
- シンポジウム 「日本語教育は学習者コーパスで変わる ―横断コーパス・縦断コーパスそれぞれの特徴―」
シンポジウム 「日本語教育は学習者コーパスで変わる ―横断コーパス・縦断コーパスそれぞれの特徴―」
- 2018/2/11
- 134 comments
日本、〒190-0014 東京都立川市緑町10−2
現在,『多言語母語の日本語学習者横断コーパス (I-JAS) 』の公開が順次行われています。この大規模な横断コーパスは,日本語教育の研究に活用され,学習者の習得過程や誤用の実態が徐々に明らかになっています。一方,学習者個々の成長や変化といった質的な面に目を向けることも,研究の重要な視点の一つです。
そこで,今回の発表では,第一部として,I-JAS の構築と研究成果をご紹介し,I-JAS の特徴を再検討します。つづいて,新たに構築中の,JFL環境の中国語を母語とする日本語学習者の4年間の習得過程を追った『北京日本語学習者縦断コーパス (B-JAS) 』をご紹介します。さらに第二部では,B-JAS のデータを用い,音声,聴解,会話における,学習者のゼロ初級から中級までの2年間の変容について発表者それぞれの観点から研究結果をご報告します。
多面的な学習者コーパスの構築により,日本語教育における言語習得の研究や学習者の指導法に対し,新たな可能性を提案することを目指します。
プログラム
13:00~13:10趣旨説明
野山 広 (国立国語研究所 准教授)
13:10~14:10第一部 : I-JAS・B-JAS の紹介
13:10~13:55基調講演「中国語母語の日本語学習者の発話に見る語用論的転移」迫田 久美子 (広島大学 特任教授,国立国語研究所 客員教授)
I-JAS の特徴を示した上で,依頼のロールプレイに見られた中国語母語の日本語学習者の語用論的転移の可能性を検討します。I-JAS のロールプレイの発話に,依頼の開始から依頼の命題までのプロセスで,日本人母語話者の発話と仏語,英語,スペイン語,中国語を母語とする日本語学習者の言語形式の比較を行った結果,中国語母語話者には他の話者には極めて少ない聞き返し (念押し) の特徴が観察されました。そして,それを中国語母語話者同士が中国語で行った場合と比較した結果,類似の傾向が見られ,聞き返し (念押し) の形式に母語の語用論的転移の可能性がみられることがわかりました。
13:55~14:10「B-JAS の特徴」野山 広 (国立国語研究所 准教授)
B-JAS は中国人日本語学習者4年間の日本語習得の縦断調査です。I-JAS の横断調査データとクロスマッチする調査項目を取り入れているため,I-JAS の同じ日本語レベルの学習者と比較が可能です。同時に,口頭能力の成長だけではなく,テストによる学習者の能力を縦断的に測っています。また,中国で現在行われている日本語学科のカリキュラムと日本語習得の関係性を見ることができます。
14:10~14:25休憩 (15分)
14:25~15:35第二部 : B-JAS を用いた研究の観点
14:25~14:55「中国人学習者における尾高型アクセントの語の習得」張 林 (北京師範大学 講師)
日本語の平板型アクセントと尾高型アクセントは単語内に下がり目がなく,語の後ろに助詞・助動詞などがない場合,平板型と尾高型は同じに聞こえます。そのため,日本語学習者にとって,尾高型アクセントの語の習得は難しいです。本研究は『B-JAS』の文字データから学習者の自発発話にある尾高型アクセントの語を抽出し,音声データを用いて学習者の発音実態と2年間の変容について考察します。
14:55~15:25「語彙習得過程における誤用の変容」費 暁東 (北京外国語大学北京日本学研究センター 講師)
音声の聴き取りの変容,学習者の語彙の聴き間違いがどのように変容していくかを具体例とともに示します。語彙の使用に関する誤用例を分析し,漢字語彙や仮名語彙にはどのような特徴が見られるかを検討します。また,誤用を修正していく過程では,母語からの影響がどのように観察され,その影響がどのように変容していくかを作文や会話のデータに基づいて検討します。
15:25~15:55「中国人日本語学習者のフィラー習得過程の実態」石黒 圭 (国立国語研究所 教授),布施 悠子 (国立国語研究所 プロジェクト非常勤研究員)
日本語学習者の話し方は,話す言葉は日本語,間に入るフィラーは母語という話し方になりがちで,こうした話し方に慣れていない日本人に,耳障りだと受け取られることもしばしばです。しかし,母語のフィラーが混じる話し方は日本語のレベルの向上につれて徐々に減少し,使われるフィラーの質も日本語学習の過程でかなり変わる印象を受けます。本発表では,こうした学習者のフィラー使用の実態を,B-JAS のデータによって縦断的かつ実証的に明らかにすることで,日本語教育におけるフィラー教育のあり方を考えます。
15:55~16:30全体ディスカッション
司会 : 野山 広
登壇者 : 石黒 圭,張 林,費 暁東,布施 悠子
コメンテーター : 迫田 久美子
16:30~16:40閉会の辞
石黒 圭 (国立国語研究所 教授)