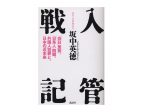西日本新聞社の「新 移民時代」が早稲田ジャーナリズム大賞を受賞
- 2017/10/31
- ぷらっとニュース
- 新移民時代, 石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞, 西日本新聞
- 603 comments

西日本新聞社が昨年12月から今年の夏にかけての長期にわたり連載した「新 移民時代」のシリーズが「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」の「草の根民主主義部門」の大賞を受賞した。
早稲田ジャーナリズム大賞は、早稲田大学が多くの優れた人材をジャーナリズムに送り出してきたことを受け、「社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自由かつ開かれた環境の形成への寄与を目的として」2000年に創設された。これまでにも質の高い新聞、出版界における活動が受賞している。
「新 移民時代」の連載記事については、その内容を高く評価し、フェイスブックの日本語教育情報プラットフォームで随時紹介してきた。「移民」という言葉自体が、ジャーナリズム界でそれとなくタブー視されているだけに、権威ある大賞の受賞は画期的なことであり、秩序ある外国人受け入れに寄与すると思われる。
受賞理由について、作家の吉岡忍氏は以下のように述べている。
コンビニ、飲食店、語学学校、工場に外国人がいる。漁港や畑や介護施設にもいる。私たちのまわりに若い外国人の姿が増えたことは、誰もが気づいている。だが、彼や彼女たちはどこから、どんな経緯できたのか、日本でどういう暮らしをしているのか、私たちはほとんど知らない。本作品は彼らが学び、働き、暮らしている現場だけでなく、出身国の送り出し機関まで取材し、その荒んだ実情を次々に明らかにしていく。根本にあるのは、異文化に不寛容なまま、3K仕事の人手不足を補うため、「留学生30万人」のかけ声の下、低賃金労働力だけを集めようとする日本政府の政策である。「労働力を受け入れたつもりだったが、来たのは人間だった」。私たちの側には、彼らを人間として見、人間としてつきあう準備がまったくできていない。そして、この多様性を拒絶し、周縁に押しやって、見て見ぬ振りをする姿勢自体が、この国の経済や政治や文化が活力を取りもどす機会を失わせているのではないか、という指摘は鋭い。
受賞者の西日本新聞社のコメント
途上国からの留学生や技能実習生が事実上の労働移民として日本を支える現実。定住外国人を生活者と捉えない「移民ネグレクト」の国策。アジア各国との最前線に根差す九州の新聞として、足元の移民問題を追いました。受賞を励みに、見えにくいものに目を凝らし、小さな声に耳を澄まして社会に伝える責任を果たしていきます。
連載は「新 移民時代~外国人労働者と共に生きる社会へ」というタイトルの書籍として近く明石書店から出版される。