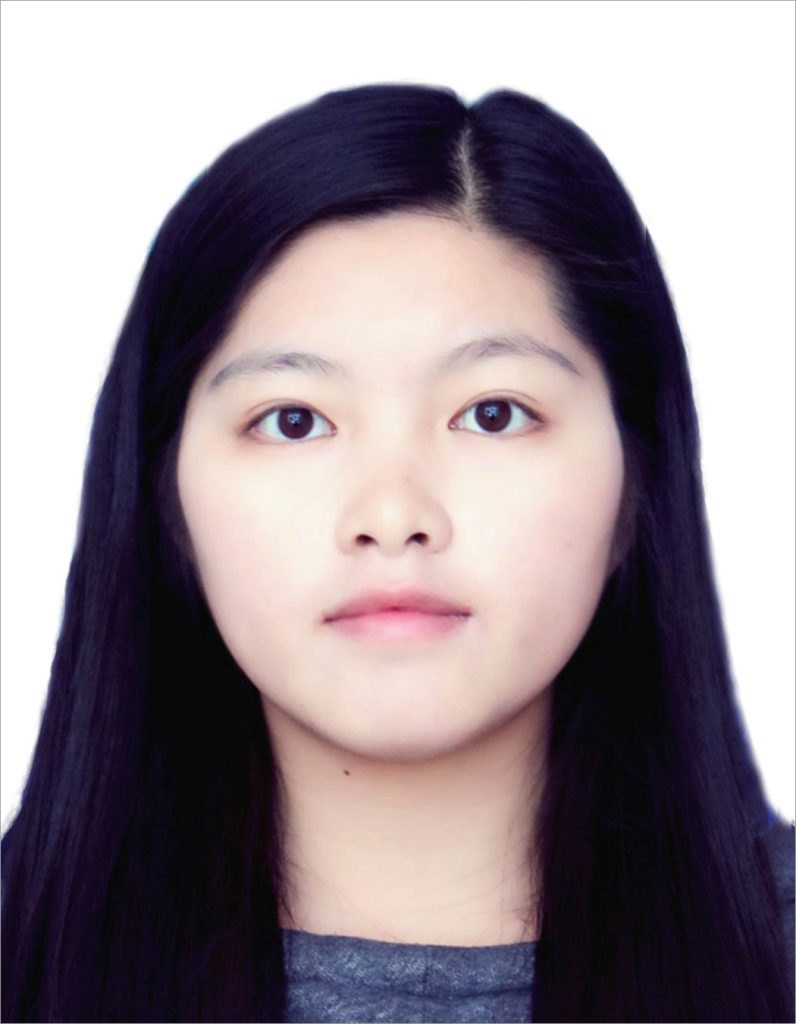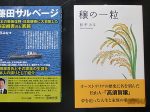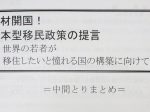中国人の日本語作文コンクール
- 2018/1/31
- 作文コンクール
- 294 comments

近年の日本における日本語学校の急増に伴い、
去年11月、日本人の先生と大学の食堂へ食べに行ったときの出来事だ。お店の前で、先生と日本語でやり取りしていると、中国人の調理師さんが興味津々でこちらをジロジロ見ていて、突然「あのう、日本人ですね。この牛肉ラーメンが一番美味しいですよ。お勧めですよ」「こちらでゆっくりお待ちください。出来上がったら、お呼びしますよ」と親切にゆっくりとした中国語で先生に話してくれた。以前は珍しい光景だったが、昨今このような優しい対応が増えている現状に、先生は驚きというよりは、むしろ喜びを感じているように見えた。
私が日本人に伝えたい中国文化のソフトパワーは漢方医学だ。
私の出身は中国の広西チワン族自治区だ。うちはもともと地元の漢方に関わる家柄で、先祖が残した優れた医術を代々受け継いてきた。
しかし、時代が変わって、西洋医術に人気がどんどん集まり、その影響から漢方医学は衰退してしまった。父は後継の役目を諦め、普通の会社員になった。
「私の言葉を世に届けたいというキミの気持ちは、そんなものだったんだね」。中村先生の言葉が心に突き刺さった。それとともに、この半年のできごとが頭の中に、次々に浮かんでくる。
私は昨年の第12回作文コンクールで、思いがけず一等賞をいただいた。段躍中先生が言うとおり、一編の作文が私の人生を劇的に変えた。一等賞のおかげで、日本大使や上海総領事をはじめ、たくさんの方々と出会い、私の世界はどんどん広がっていった。
「麗ちゃん、来週青島へ旅行に行くんだけど、よかったらちょっと案内してくれない?」
先日、日本人の友達A君から旅行の案内を頼まれました。「いろんな観光地を回りたいけど、中国語が分からなくてね」と、私をたよってきたようでした。
実は、日本語を勉強してからの3年間、私は何度もこのような依頼を受けました。「観光地に日本語の説明看板がほとんどないから、ただ見るだけで、この建物は何のために建てられたのか、この彫刻にはどんな意味があるのか、よく分からない。説明してくれる人がいると本当に助かるよ」。一緒に青島を観光していた時、A君がそう言いました。
里美ちゃんへの返事 ――中国の新しい魅力「環境保護の価値観」
拝復 里美ちゃん
お久しぶり! 最近どうしてる? 別れてもう半年経ったね。去年九月、大学の短期プログラムで来ていた里美ちゃんと一緒に過ごした日々が、昨日のことみたいだよ。一緒に授業を受けたり、食事したり、上海のあちこちを歩き回ったり、ほんとうに楽しかったよね。
里美ちゃんはこの間のメールの中でこんなことも言ってたね。
「中国って本当に広い。歴史的景観も多いし、料理も地方色が豊かだから、あちこち行ってみたいな」。里美ちゃんがそう言ってくれて、私もうれしい。でも里美ちゃんは町の人々のよくないマナーや習慣なども見ていたから、そのことで中国へのマイナスの印象を持ってしまったよね。
カンカン、コンコン、ダダダダン。
剣がぶつかり、影が舞う。足音が響き、棒と槍をかいくぐる。
私の故郷、広東省の掲陽市にある伝統舞踊がこの「英歌舞」だ。日本の時代劇の殺陣や中国拳法の演舞にストーリーをつけたものと言えば想像しやすくなるだろうか。そのストーリーは日本でも有名な水滸伝だ。