小中学校における日本語教育に関する提言 ~『教科』の前に日本語教育を~
- 2018/6/10
- 時代のことば
- 帰国子女, 教科
- 195 comments

小中学校における日本語教育に関する提言

外国から転入してきた児童生徒は私の住んでいる仙台にもかなりたくさんいるようです。しかし、私の見たところでは、そうした子供たちのための学校側の受け入れ体制は到底十分とは言えないようです。もちろん予算も人材も限られているわけなのですが、重要なのはそうした制約の枠内で効果的な日本語教育を行うためのシステムをうまく作ることだと思います。私がこのために提言したいのは次の三点です。
- 日本語の話せない転入生にはまず日本語を十分に習得させる必要がある。この段階では、該当の児童生徒を通常の授業に参加させるべきではない。
- この際、通常の授業に参加できるようになるまでは、該当の転入生が自主的に原級に留まることを認めるべきである。
- 日本語の教材としてはできる限り自習教材を開発して使用すべきである。
以下では個人的な体験を交えて、なぜこのようなやり方が望ましいかを説明したいと思います。
小学校への編入
私は諸般の事情で25年ほどオランダに住んでいたのですが、平成27年に帰国して現在は妻と下の娘と三人で仙台に住んでいます。帰国以前は家庭ではオランダ語で話していましたので、娘は日本に移住してきた時には日本語がまったく話せませんでした。しかし、「最近では日本にも外国人はたくさん住んでいるから、受け入れシステムもできているだろうさ」と娘に言い聞かせて、普通の公立小学校の六年生に編入してもらいました。ところが、新学期が始まってみると、受け入れシステムが意外にもかなり貧弱なものだということに気づきました。一日に一時間ほどは外国人児童受け入れ担当の先生から別室で日本語を教わることができるのですが、それ以外の時間はクラスの他の生徒と一緒に通常の授業に参加していたのです。あたり前のことですが、授業で話されていることは何ひとつ理解できません。九月に編入されてから三月まで半年間、私の娘は一日の大半を呆然と座って過ごしていました。
実際のところ、われわれの側にも問題がなかったわけではありません。なかば無理やり日本に連れてきてしまったので、最初の二年ほどの間、娘は日本に対する拒絶反応を起こしてしまっていたのです。しかし、日本語の話せない生徒がいきなり転入してくるといった事例は今では特に珍しいものではありません。いずれにせよ、非常にたくさんの外国人の子供たちがいわば教室という孤島に置き去りにされており、どこからも助けが得られないという状況にあるという事実は直視する必要があります。
上のような状況は現場の先生方の怠慢によって生じたものではありません。問題はあくまで、伝統的な日本の教育システムではこうした「日本語の話せない転入生」はまったくの想定外の存在であり、したがってこうした転入生に対応するためのシステムがないという点にあります。
基本的な誤解
小学校の先生方とは何回か話し合いをもちましたが、その際に気づいたことがあります。それは、現場の先生方が「教科を教える」ということに非常に強い執着をもっているという点です。先生方には、「日本語がわからなくても、教科の内容だけは何が何でも教えなくてはならない」という思い込みがあるようなのです。
この問題が奇妙な形で露呈したことがあります。小学校で、娘が学校からいきなりiPadを支給されたのです。「これは何なんですか」と先生に訊いてみたところ、「これに通訳アプリをインストールして、授業を聴いてもらうんです」という答えでした。私は絶句してしまいました。通訳アプリの精度の低さという問題はさておき、そんなことをしても何にもなりません。転入生には日本語を習得して自立した人間として生活していけるようになることがもっとも重要な課題であるはずで、通訳アプリ(もしくは人間の通訳)などが介在する余地はありません。そのようなやり方はむしろ、生徒が日本語を習得するための機会を奪うことにしかなりません。ことによると上の方から「日本語がわからなくても教科だけは教えるように」という指導がなされているのかもしれませんが、おそらくこの誤解が、小中学校での日本語教育システムの構築に対する非常に大きな障害になっているように思われます。
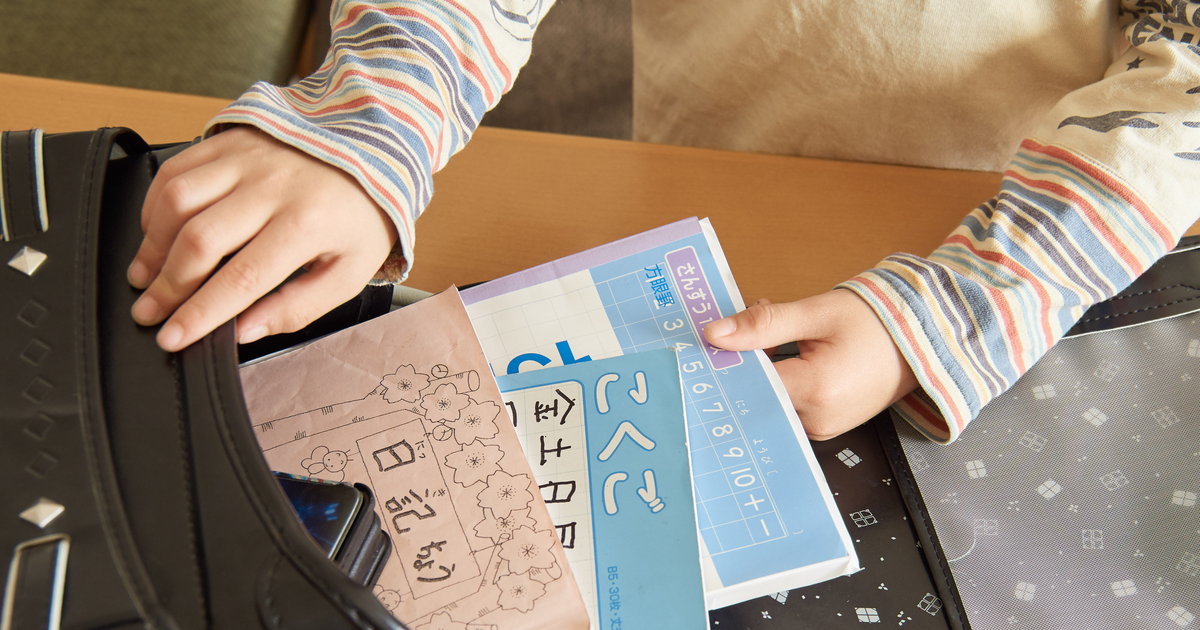
「日本語を学ぶこと」と「日本語で学ぶこと」
上の提言にもどりましょう。まず第一点の「日本語の話せない転入生をいきなり通常の授業に参加させるべきではない」という点ですが、これは「日本語を学ぶ」段階と「日本語で学ぶ」段階をはっきり区別すべきだということです。ちなみに文科省では「JSLカリキュラム」というものを発表していますが、これは「日本語で学ぶ」ことを念頭に置いたもので、実際のところは上で述べたような誤解を助長するようなものになっています。
私の妻は移住前にはオランダで教師をしており、中学校で外国人生徒の受け入れに関わったこともあります。オランダの中学校では普通、外国からの転入児童・生徒にはまずオランダ語を集中的に教え、オランダ語がある程度できるようになった段階で通常のクラスに編入するようです。これはよいやり方だと思います。西ヨーロッパの多くの国ではこの方式だと思いますが、聞く所によると英語圏では事情はやや異なっているとのことです。
原級留置
通常の授業をまったく受けさせないと言うと、「それではそのまま卒業させるのか」という声が聞こえてきそうです。確かに、高校入試などもあるわけですから教科を教えないわけにもいきません。この問題に対する解決は、第二点として述べたように「生徒が日本語を学んでいる間は自主的に原級に留まることを認める」ことでしょう。この場合、小学校六年生で日本に来て一年間を日本語の習得に費やした場合、その後で編入されるのは中学一年ではなく小学校六年になります。
このような考え方は現場の先生方にとっては非常に抵抗感のあるもののようです。日本の先生方は「クラスのみんなと一緒に」という考え方を非常に大切にしているからです。しかし、いかに子供であっても、言語的なコミュニケーションなしに情緒的な絆を結ぶことなどできません。「クラスのみんなと一緒に進級しなければかわいそう」というのはただの思いこみで、本人にとってはむしろ大迷惑でしょう。

自習教材の使用
最後にリソースの問題です。実際にはおそらく、各小中学校に外国からの転入生向けの日本語集中コースを設置するためには非常に多くの予算が必要となります。また、転入生の多くは英語も話せないと思われますが、各学校ですべての言語に対応することは事実上不可能です。
この問題を解決するためのもっともよい方法は、文科省のほうでできるだけ多くの言語に対応した自習教材を作成し、文科省のウェブサイトに置いてだれでも自由に利用できるようにすることです。(インタラクティブなウェブ・アプリケーションにするのが理想でしょう。)
むすび
私は娘が中学校に上がったときに市の教育委員会に陳情に行き、当分市販の自習教材を使って日本語の自習をさせてほしいと希望しました。この希望は受け入れられ、娘は最初の一年半ほどを日本語の習得にあてました。紆余曲折はありましたが、今ではどうにか通常の授業についていけるようになりました。関係者の皆様に感謝したいと思います。




























