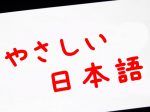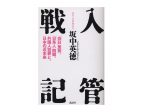外国人集住都市会議「おおた2018」――「開かれた共生社会」を全国に
- 2019/2/1
- 多文化共生, 時代のことば
- 外国人集住都市会議
- 69 comments

外国人集住都市会議「おおた2018」――「開かれた共生社会」を全国に
日系ブラジル人など外国人が多く住む15の市や町でつくる外国人集住都市会議。その首長会議「おおた2018」が1月29日、群馬県太田市で開催された。昨年の臨時国会で入管法が改正され、政府の「外国人材受け入れ・共生のための総合的対応策」が策定されて初の首長会議だ。議員立法で日本語教育推進法制定への動きもあり、会議を締めくくる「おおた宣言」は「特定地域の課題とされた外国人労働者の受け入れや共生社会の実現は、今後、日本全体が課題として議論・共有して取り組んでいく必要がある」と述べ、全国に多文化共生の議論を呼びかけた。
外国人集住都市会議が発足したのは2001年5月。外国人住民が増えることで「地域で顕在化しつつある問題の解決に積極的に取り組んでいく」のが目的だった。浜松市長の呼びかけで当初は21の市と町が集まった。誤解を恐れずに言えば、行政の「お荷物」としての外国人問題にどう対処すべきか、そんな問題意識で出発したように見えた。以後、様々な課題を洗い出し、その解決に向けて連携し、国への提言や要望を発信してきた。
首長会議には総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、内閣府などのおおむね課長クラス以上の幹部が出席してきた。公開の場で首長側と政府の幹部が意見を直接ぶつけ合う建設的な催しだ。地方が抱える課題は、「言葉の壁」、ゴミ出しなど生活のルール、外国人児童生徒の教育など切実なものばかり。行政には住民の苦情が様々な寄せられてきた。政府側にも問題意識を共有する熱い想いの幹部が何人もいた。その結果、「首長の声」が政府を動かしてきたのも事実だ。
2006年には総務省が地方自治体のための外国人受け入れの指針「多文化共生プラン」を作成し、政府の関係省庁の連絡会議が「『生活者としての外国人』のための総合的対応策」を策定した。定住を見越し「生活者としての外国人」という概念を政府が打ち出した意味は大きい。2012年には外国人の住民登録が始まり、外国人が「市民」や「町民」として住民基本台帳に掲載された。こうした動きをマスメディアが大きく取り上げることはなかったが、日本は「多文化共生の道」を着実に歩んできた。それを引っぱってきたのが外国人集住都市会議だ。
外国人集住都市会議は規約を改正し、「外国人住民の持つ多様性を都市の活力として、外国人住民との共生を確立することを目的する」との考えを示した。時代の流れを的確に見据えたものだ。実際、日系ブラジル人の第二世代などがグローバル人材として社会で活躍するケースが増えている。都市の活力を支えているのが、外国人の労働力であることは否定できない事実だ。
今回の「おおた2018」には、太田市長をはじめ浜松市、群馬県大泉町、愛知県豊橋市、三重県四日市市の首長、政府側からは法務省、文科省、文化庁、厚生労働者省、総務省の担当局長、課長らが出席。日本国際交流センター執行理事の毛受敏浩氏の基調講演のあと、「新たな外国人材の受け入れについて」と「外国人住民が多様性を活かし活躍できる環境整備について~日本語教育を中心として~」の二つのセッションで「地方VS政府」の意見の交換が行われた。
セッションでは政府側から佐々木聖子法務省入国管理局長が出席したことが注目を集めた。佐々木氏は一連の入管法改正や総合的対応策を取りまとめの中心人物で、4月に発足する出入国在留管理庁を主導するはずだ。佐々木氏はセッションで新たな在留資格の「特定技能」の創設に関連して「外国人材の支援」を強調した。外国人の「管理」が仕事の入管行政からみれば、「支援」というミッションに向かい合うことは意識の切り替えが必要になるはずだ。役所の側も改革をポリシーにする。佐々木氏はそう考えているようだ。
とは言っても、「生活者としての外国人」の支援の実務の大半は地方自治体が担う。政府の総合的対応策に盛りこまれている施策はほとんどが後方支援である。地方自治体が求めるのは、新たな財政支援だ。政府は126の施策に224億円(後日
セッションでは5人の首長がそれぞれの市や町の「多文化行政」の取り組みを紹介した。外国人の人口比率が約18%と全国一の大泉町以外の自治体も外国人比率は全国平均の2倍を超えている。日本語教育や外国人児童の学校教育、外国人学校、医療福祉などの社会統合政策の取り組みなどは、当然、他の自治体より数段進んでいる。外国人集住都市会議の参加都市からすれば、「ようやく政府がことの重要性に気づいてくれたか」という受け止めではないか。
浜松市の場合は多文化共生の国際的なイベントを開催したほか、2017年に欧州評議会が主導する「インターカルチュラル・シティ・ネットワーク」に加入した。欧州で最も進んだ移民政策に取り組む都市のネットワークだ。浜松市は外国人児童の不就学をゼロにしようと市が一丸となって取り組んでいる。太田市はブラジルにまで教師を派遣して研修をさせている。豊橋市は日本語教育だけでなく英語教育の充実により、「多言語人材」の育成に言及した。大泉町は歯をくいしばって自主財源をねん出し、多言語化などの取り組みをしている。
こうした取り組みをみると、政府が鳴り物入りで打ち出した総合的対応策がかすんでしまう。外国人集住都市会議の加盟都市は、まさに「共生の先進都市」なのだ。「外国人労働者の受け入れが大都市圏に集中しないよう措置をすべきだ」と声があるが、果たしてそうか。外国人集住都市会議の市や町はほとんどが中小の規模の都市だ。大都市であっても魅力のない都市からは外国人は逃げていく。外国人観光客が、「おもてなし」の行き届いた魅力的な地方の町にも足を運ぶようになってきたことにも注目したい。
セッションでコーディネーターを務めた山脇啓造明治大学教授は日本人の側にも「やさしい日本語」を広めることを通じて、日本人と外国人がより円滑なコミュニケーションがとれる社会を築くよう提案した。また、「外国人集住都市会議の首長の知見を、これから外国人を受け入れる自治体に広げていくことが重要だ」と総括した。外国人集住都市が人口減少時代の地方行政をリードするのではないか。「おおた2018」は、そんなことを予感させる会議だった。
石原 進