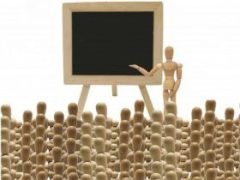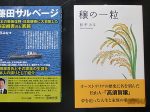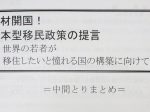文化庁がまとめた「日本語教師の資格の在り方」とは
- 2020/4/25
- ぷらっとニュース, 日本語教育
- 608 comments

文化庁がまとめた「日本語教師の資格の在り方」とは
文化庁の文化審議会国語分科会は3月10日、「日本語教師の資格の在り方について」と題した報告書を公表した。この中で、日本語教育の質の向上を目指し、新たに「公認日本語教師」という資格の創設を提言したことが注目される。今後、日本語教師の育成はどのように進められるのか。以下、報告書のポイントを紹介する。
在留外国人は約283万人(2019年6月末)にのぼり、国内の日本語学習者数も約26万人と増加傾向にある。これに対し、それを支える日本語教師の約6割がボランティアであり、職業としての日本語教師は約4割の1万9000人にとどまっている。報告書は、今後、留学を目的とする日本語学習者のみならず、生活者向けや特定技能といった就労者への日本語教育のニーズがより一層高まる中、そのニーズに応えられる日本語教師を養成し、質の高い日本語教育を提供することを課題として挙げている。 そうした中で昨年6月、日本語教育推進法律が成立し、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるよう、養成及び研修体制の整備、国内における日本語教師の資格に関する仕組みの整備等の施策を講ずる旨の規定が盛り込まれた。日本語教師の資格制度創設は、この法律に沿った提言だ。
現在は、法務省出入国在留管理庁がまとめた「日本語教育機関の告示基準」の教員要件が実質採用等で用いられている。以下が告示基準の教員要件である。
・大学、大学院で主専攻・副専攻
・公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格
・学士以上かつ日本語教師養成講座420時間修了者
・上記と同様以上の能力があると認められる者
→海外の大学または大学院で日本語教育に関する過程を卒業した者
→学士以上を有し、告示校の教員として1年以上従事し、3年を超えて日本語教員の職を離れていない者
→学士以上を有し、大学又は大学院で26単位以上の日本語教師養成を履修(うち教育実習1単位以上含む)した者(通信の場合は、26単位以上の授業科目 のうち6単位以上が面接授業)
一方、新しく設けられるとみられる「公認日本語教師」の資格取得要件は、以下の3つである。
①日本語教育能力を判定する試験への合格
②教育実習の履修(45コマ以上、クラス形式・2コマ(90分)以上の教壇実習を含む)
③学士以上
なお、「公認日本語教師」の有効期限は10年となっており、期限内に更新講習の受講が義務付けられている。この資格制度創設に伴い、告示基準の教員要件を満たす教師を「公認日本語教師」に移行するには、十分な移行期間を設けることになっている。この移行に関して、ポイントになると考えられる点は以下の2点である。
一つ目は、大学における主専攻・副専攻及び文化庁届け出の日本語教師養成研修を受けたとしても、原則「①日本語教育能力を判定する試験への合格」が必要となる点である。この試験の内容に関しては、「必須の教育内容」とされているものが、現在実施されている日本語教育能力検定試験の範囲と重なっている。今後、詳しい実施方法や難易度等が検討されると思われる。
二点目は、日本語教師養成講座修了かつ日本語教育能力検定試験に合格した学士号を持たない日本語教師についてである。新たに設けられる資格の要件①と②を満たすが、③を満たさない場合だ。(現在の日本語教育検定試験に合格していることから①の要件を満たすと仮定)大学進学率が現在よりも低い時代の日本語教師は一定数おり、特に女性が多いこの業界では該当する人も少なくないと考えられる。
「公認日本語教師」は、名称独占の資格であり、要件を満たしていなければ、「公認」を名乗れないだけであり、日本語教育という業務そのものは可能である。ただし、活躍の場が今後拡大するとは考えにくい。
資格制度創設の目的でもある「質の確保」と「多様性の確保」との折り合いのはざまにいる日本語教師も多いと考えられる。報告書に盛り込まれた提言をどう具体化していくのか。日本語教育の質の向上は喫緊の課題である。しかし、今後、さらに議論すべき点も多々残されている。
にほんごぷらっと編集部 徳田淳子
日本語教師の資格の在り方について(報告) 令和2年3月10日https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/92083701_01.pdf