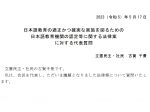公認日本語教師の報告書に対するパブリックコメント―—吉開章氏はこう考える。
- 2021/8/25
- ぷらっとニュース
- 公認日本語教師, 吉開章, 国家資格, 日本語教育能力検定試験
- 公認日本語教師の報告書に対するパブリックコメント―—吉開章氏はこう考える。 はコメントを受け付けていません

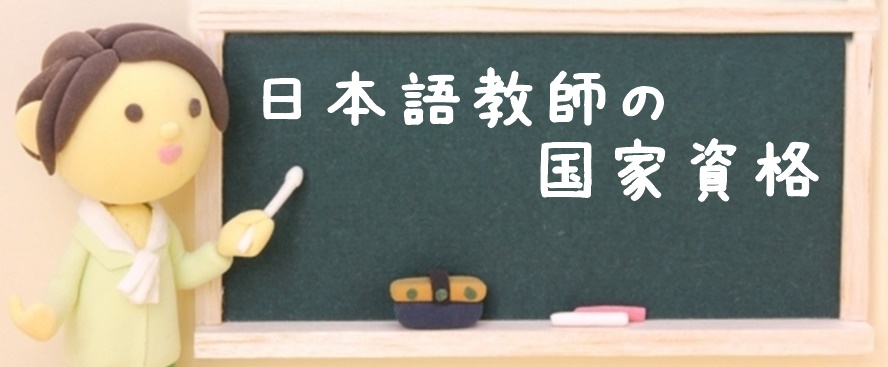
公認日本語教師の報告書に対するパブリックコメント―—吉開章氏はこう考える。
文化庁は、日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議の意見を参考にして日本語教師の初の国家資格である公認日本語教師の制度創設に向けた報告書をまとめた。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/pdf/93324301_01.pdf
正式には「日本語教育の推進のための仕組について(報告)」と題する報告書に関して、文化庁は意見(パブリックコメント)の募集を行っている。提出期限は9月17日で、応募要領は以下の通り。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/ikenboshu/nihongoiken_suishin/index.html
「にほんごぷらっと」は、パブリックコメントの公開することを通じて、より議論を深めることが必要だと考え、まずは「やさしい日本語ツーリズム研究会」代表で、『入門・やさしい日本語』認定養成講座をプロデュースする吉開章氏のパブリックコメントを紹介する。吉開氏は日本語学校などで教鞭をとっているわけではないが、420時間の日本語教師養成講座を修了したほか、日本語教育能力検定試験にも合格。日本語教育に関する「能力」を十分備え、各地の自治体の要請を受けて「やさしい日本語」に関する講演活動を精力的に行っている。「にほんごぷらっと」の世話人に一人でもある。以下、吉開氏のパブリックコメントを掲載する。
*******
文化庁「日本語教育の推進のための仕組みについて」に関する意見募集に対して、以下のパブコメを送信しました。現在の有資格者の方々も、短くてもいいのでパブコメを送りましょう!
——————–
○日本語教師の資格について―10について
現在の日本語教育人材の新制度移行に関して意見を申し述べる。ここでは「『日本語教育機関の告示基準』第1条第1項第13号の教員要件を満たす」ものを「有資格者」、公認日本語教師資格を「新資格」と記す。
報告書8ページ「10. 現職日本語教師等への資格取得方法」では、
「日本語教育機関の告示基準」第1条第1項第13号の教員要件を満たす現職日本語教師等が公認日本語教師の資格取得を希望する場合、原則として筆記試験合格及び教育実習履修・修了の要件を満たした上で公認日本語教師の資格を取得することとする。ただし、質が担保されている機関で一定年数以上働く等、教育の現場における実践的な資質・能力が担保される者に関しては、教育実習の免除などの配慮を検討する。(実践的な資質・能力の確認方法については慎重に検討を行う。)
とあるが、様々な懸念を持っている。
意見1)現行の日本語教師有資格者に対し、現職でないものも含めて十分な新資格移行措置を取るべきである。
有資格者の中で「現職日本語教師等」を指した項目となっており、現職以外の有資格者についての言及が曖昧である。現行制度でも教育機関での指導以外に、多文化共生社会づくりに資する知識・能力として有資格者となった人も多数いる。報告書案9ページでは「多様な日本語教育を行う機関の質が保証されていくことは、公認日本語教師が活躍することが期待される場を明確化することにつながるものである。」とあるが、新資格の導入が日本語教育人材の活躍の場を教育機関に限定する方向に強化される恐れもある。配慮の対象となっている「実践的な資質・能力」についても、教室での指導に限定しているようにも解釈できる。新資格の導入によって、やさしい日本語の普及活動など、日本語教育の専門性を教室外で生かしている人材の評価が相対的に下がるようなことがあってはならない。
意見2)現行の日本語教育能力検定試験合格者については、新制度の筆記試験1・2双方に合格したものとみなし、実習のみを課すことで新資格に移行すべきである。
「現職日本語教師等が国家資格取得を希望する場合、原則として筆記試験合格及び教育実習履修・修了の要件を満たした上で公認日本語教師の資格を取得することとする」となっているが、これではこれまでの有資格者は「原則として」新資格に満たない資質であると言っているに等しい。有資格者全員が一から新国家資格の試験を受ける必要があるとした場合、現行の主要な試験である日本語教育能力検定試験とどのような違いがあるというのか。知識を問う国家試験の範囲は幅広く、知っておくべき重要な用語などが多数あるが、調べればわかる知識を問う試験は1度で十分である。
意見3)仮に現行の日本語教育能力検定試験合格者になんら移行措置が講じられないとした場合、受け直しによるメリットが集中する公益財団法人日本国際教育支援協会は指定試験実施機関としてふさわしくない。
仮に筆記試験1・2の実施機関が、現行の日本語教育能力検定試験を運営する公益財団法人日本国際教育支援協会(以下JEES)となった場合、同団体が運営してきた過去の日本語教育能力検定試験合格者すべてが受験し直すという施策は、これまでも事業収益を得てきたJEESに莫大な追加利益をもたらす。現行の日本語教育能力検定試験合格者が一切評価されず、新筆記試験の一部または全部を受け直す必要があるとするなら、JEESのこれまでの作問のノウハウはゼロベースで考慮すべきである。さらに言えば、新制度設計が結果としてJEESへの利益誘導をうたがわれないよう、別の団体を指定試験実施機関とすべきであろう。
意見4)新国家資格移行に際しては、「8.更新講習」にある研修の機会を文化庁の予算事業として新制度導入初年度の早い段階で実施し、現行の日本語教師有資格者に受講させるのが望ましい。
日本語教育能力検定試験をはじめとする現行の教員要件は、日本語教育機関の告示基準という国のガイドラインにも採用されているものであり、新資格で求められるものと根本的に違う要件であることはありえない。現行の有資格者に対しては新旧制度の差分を十分に理解・習得できるような研修機会を提供すれば十分であると考える。本報告書案には「更新講習」を文化庁としての予算事業で行うことも明記されており、初年度にこの講習に相当するものを実施することが望ましい。新しい試験を実施する上でも、差分を明記することは重要であり、現在の有資格者の移行措置だけに関わることではない。
◆「にほんごぷらっと」は、文化庁に送付したパブリックポイントの公開を希望する方があれば、ぷらっとニュースとして掲載します。受け付けは以下のメールアドレスで行います。