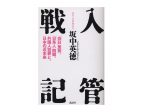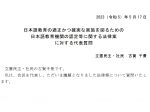10月の入国解禁は今後の留学生政策の最大の鍵となる
新型コロナウイルスの感染拡大で日本留学ができない海外の学生らの声を発信する「コロナ禍の日本留学の扉を開く会」。留学ビザを出しながら入国の規制が長期化し、留学生の「日本離れ」が危惧されている。「囲む会」のコアメンバーで新宿日本語学校校長の江副隆秀さんが、コロナ禍で日本留学が直面する課題について投稿してくれた。以下、「にほんごぷらっと」で紹介したい。
10月の入国解禁は今後の留学生政策の最大の鍵となる
G7諸国で留学生を入れていないのは日本だけ
日本社会はオリンピック後のパラリンピックの最中でもあり、コロナの感染拡大で多くの人が内向きになるのも無理がない。確かにコロナ禍は身近に存在する生死に関わる問題だ。これに関する情報は重要で、それを否定するものではない。
ただ、世界は動いている。外国人留学生の件もその一つだ。日本では、ウイルスは外国から来るので、水際対策の一つとして外国人留学生を受け入れないのは当然だという風潮がある。
しかし、「G7諸国の中で、日本だけが外国人留学生を受け入れていない」と言ったら驚く人がいるかもしれない。「日本も国費留学生を入れているでしょう」という声が出るかも知れないが、来日する留学生総数から言ったら僅かだ。
G7諸国で、際立って感染者が多かった米国も、英国も、コロナ禍が始まって以降、一度も外国人留学生の受け入れを止めたことはなかった。昨年の6月からフランス、イタリア、ドイツが外国人留学生の受け入れを開始し、一番遅いカナダでも昨年の10月に受け入れを開始している。
G7の中でいまだに留学生を受け入れていないのは日本だけだ。G7以外で、留学生を受け入れている国をあげれば、アイルランド、韓国、スイス、スペイン、フィンランド、英語教育で有名なマルタ、東南アジアではマレーシアなどがある。
日本と同じように規制をしている国もある。オーストラリアやニュージーランドがそうだ。しかし、どちらの国も、この後いつ入国できるかの発表をすることになっている。少なくとも、留学のサイクルのロードマップを発信しようとしている。
東京オリンピックで、選手及び関係者合わせた来日者数42,681人中、空港で陽性が判明したのは37人と、率でいえば0.09%。さらに選手村や会場での検査数624,364回中、感染が確認されたのは138人で、0.02%と、非常に低い結果が出ている。
韓国政府は、今年2021年度の上半期に入国した留学生34,000人中、入国時の検疫期間中含め、感染者は255人、0.75%だった上、「海外から入国した留学生による大学および地域社会への追加感染の事例なし」と公式ページに掲載している。各国で留学生が大きなクラスター源になったという報告は聞かない。
計画的偶発性理論で、近隣諸国に留学先を変更
ドッグイヤーと言われる昨今、急激な社会の変化を理解している人々は、人生におけるキャリアプランを重要視する。そして、そのキャリアプランには空白は許されない。例えば、留学しようと思い立った時に、自分の人生の中で、いつが留学に適しているのかなどを計画し、実行する。
ジョン・D・クランボルツ(心理学者)が提唱した「計画的偶発性理論」というセオリーがある。これは、もし、日本に留学しようと思っても、日本には入れないとわかった時、その時点の目的は留学であるから、近隣諸国に留学先を変えて、留学という当初の目的を果たそうとするような例も含まれる。
留学先を他国にしなさいというメッセージ
それは、日本が、「外国人留学生は、今は(日本はコロナで大変で)入国できない」というメッセージを出したとしても、それを受け取る外国人留学生の側は、「理由はともあれ、行き先を変えてください」という日本からのメッセージとして受け取ることになる。
入国制限のため日本留学を諦め、韓国に留学先を切り替えたスペイン人女性がいる。父親が日本のアニメが好きで、少しだけ日本語を理解していたそうだ。その父親から5歳の時に「ひらがな」を習ったのが日本に興味をもった最初で、10代後半には家族旅行で来日も果たしている。その後、2020年9月にスペインの大学を卒業し、日本留学を決心、日本語の勉強を続けていた。そして、2021年4月の入学者として日本留学の手続きを完了。ところが、日本は、留学生は受け入れない。
そこで、6月に韓国の大学の語学研修所に方向転換。今後1年韓国での留学を続ける方向で、韓国の入国手続きがスムーズだったことに満足している。韓国に行った理由を聞くと、やはり基本的には「時間がもったいない」ということだった。
日本として、「もったいない」というのは、こうした学生を失っている事実だろう。実際、韓国に留学先を変更している学生は、彼女だけではない。この機に韓国へのシフト現象が起きている。海外から見たら、日本も韓国も大きな違いはないのである。
ビジネスパーソンも大事だが、留学生は未来の宝
留学生に多いのは20代から30代の青年だ。この年齢は、文化に対する受容性が高く、理解のために留学先に同化しようとする傾向も強い。10年後、20年後に、ヨーロッパで日本と異なる発想で日本批判の発言を始める人が出るというような、今は想像できないことが起こるかも知れない。
日本では、ビジネスが一番で、まず、ビジネスパーソンの入国が第一のように思われている。しかし、ビジネスでは入国制限を理由に取引先を容易に変更するのは難しい。それに対して、留学生個人が行き先を変えるのは、一晩で十分だ。一度も留学生に国を閉さなかった英米に比較し、留学生を受け入れていない我が国の状況は、その重要性に気づいていないということの証明なのかも知れない。
未来予測も必要・10月入国は必須
また、少し先に起こる可能性についても、述べてみたい。
例えば、来年4月に日本が留学生に入国許可を出したとしよう。その場合の最大の懸念は大量のキャンセルである。2020年度の未入国者のうち、34%ものキャンセルが出たという調査結果がある(日本語教育機関関係6団体 2021年3月12日作成データ、242校回答)。10月入国が実現しなかった場合は、少なくとも50%以上のキャンセルが予測される。
キャンセルが少なかった場合は別の問題が発生する。2020,21,22年に滞留している3年分の留学生が一気に入学することになり、未だコロナ状況が不安定な中、宿舎、教室に収容しきれなくなる。そもそも定員管理上、このことに対応できるのであろうか。
G7諸国ではそのような混乱は発生しないことは、ここまで読んでくださった読者の方には理由を説明するまでもないだろう。
こうした、予測される混乱まで含み、G7諸国と同じように、日本は、留学生の受け入れを開始すべきだろう。そして、混乱を防ぐ時期は、この10月である。この10月を逃したら、混乱は防げない。日本留学はリスキーであるという風評が確定し、高度人材ほど離れて戻らないだろう。
もう一つ、アドラー心理学などから類推されることは、「」を言われた側は、「自分の存在の否定」と受けとめ、その裏返しは、「否定されたことへの恨み」となる可能性が高い傾向があるということだ。
「日本のこと?もう興味ないよ」。今は、そういう外国人学生をたくさん生み出す可能性がある瀬戸際に来ている。10月の留学生受け入れは、真剣に検討し、解決しなければならい課題だ。
なお、こうした留学生の声は去る8月18日に「コロナ禍の日本留学の扉を開く会」が開いたンターネット・イベント、が現在YouTubeで「日本からは来られるのになぜ私達は日本に行けないの」という題で以下のURLで視聴できます。ぜひ、ご覧いただきたい。
ダイジェスト版(8分)
https://drive.google.com/file/d/1oxVhAGIpF7mbsPYuBbHKrZuQQXYYPYdH/view
学校法人江副学園
新宿日本語学校 江副隆秀