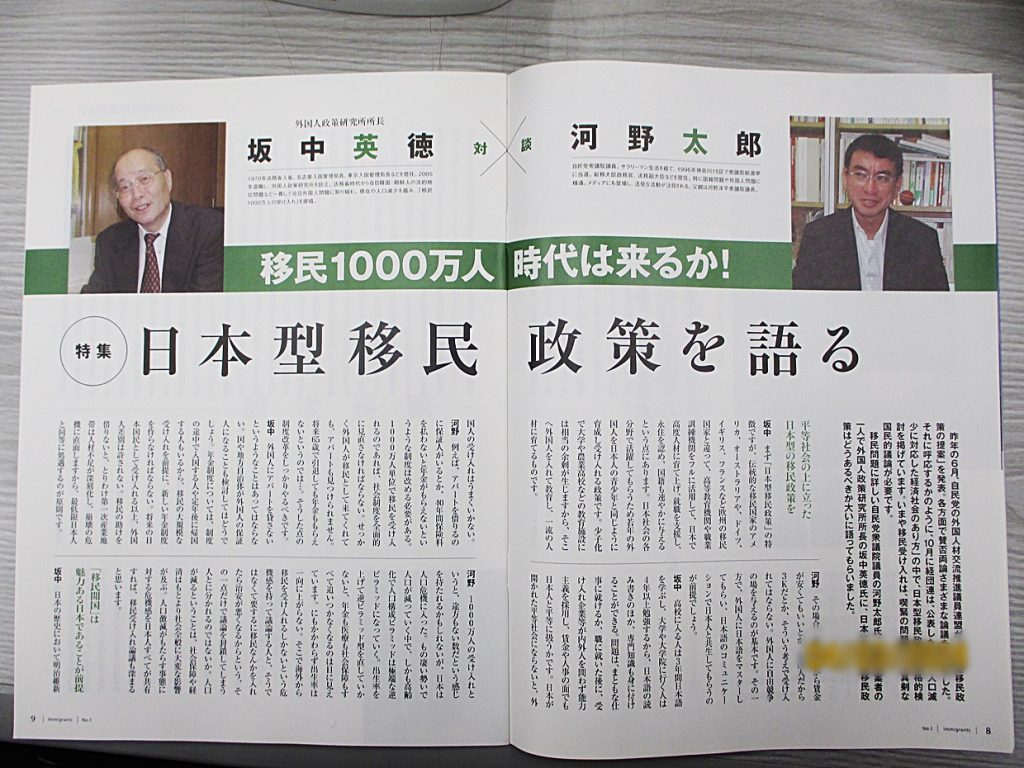移民政策の先駆者・故坂中英徳さんを偲んで 第二話 日本型移民政策の提言(下)
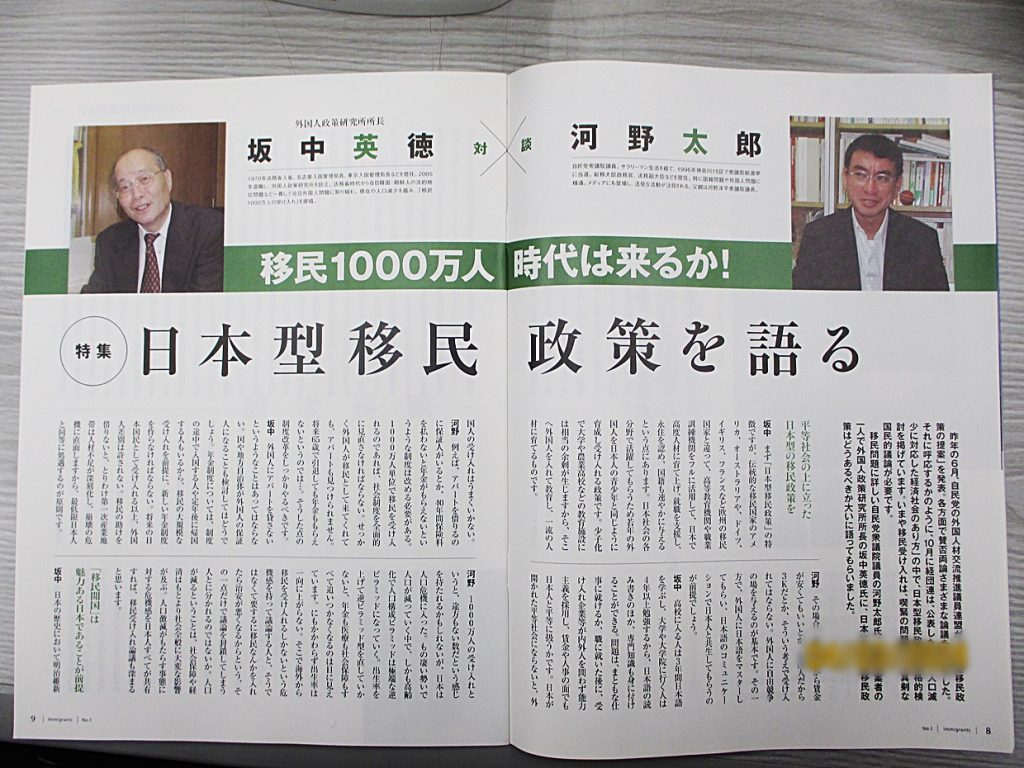
移民政策の先駆者・故坂中英徳さんを偲んで
第二話 日本型移民政策の提言(下)
元東京入管局長の坂中英徳さんが残した最も大きな功績は、自民党外国人材交流推進議員連盟の「日本型移民政策の提言」の原案を作成したこと――私は前回の企画記事(上)でそう書いた。提言の中身を具体的に振り返り、その功績のポイントを述べてみたい。
2008年6月初旬に坂中さんから提言案の概要を見せられ、その前文を書いてほしいを頼まれた。当然、その全文を何回か読み直した。その時には「なるほど」と思ったものの、それがどの程度の価値を持つものなのか、余りイメージが湧かなかった。ところが、いま読み返してみると、その理念から政策まで、多岐にわたり政府がそれを踏襲しているではないか。
議員連盟が提言を発表した時、「1000万人移民受け入れ」の見出しが新聞に載った。50年で1000万人を受け入れるわけだから、平均すると年間20万人だ。今からみれば現実的な数と言えるのではないか。しかし、当時はすぐにでも1000万人の移民が日本にやってくるかのように受け止められた。「反移民」の保守グループが意図的にそう宣伝したように思えた。一部の人にはショッキングなニュースだったかも知れない。
私は、自身が創刊した多文化情報誌「イミグランツ」で坂中さんと衆院議員の河野太郎さんの対談を掲載した。テーマは「日本型移民政策を考える」。その考えを少しでも多くの人に伝えたいと考えた。
さて、肝心の提言の中身だが、事前に坂中さんから「1000万人という数字はどうでしょうか」と意見を求められた。私は「ヨーロッパ各国の移民受け入れは人口の10%前後ですから、日本でもその割合を考えたら1000万人でいいのでは」と答えた。もっとも、坂中さん自身は「移民1000万人」という数字を朝日新聞の紙上で発表し、その数字のインパクトの大きさをわかっていたように思う。
在留外国人数は2000年代に入っても増加を続け、2007年末には256万人にのぼった。ところが、翌2008年にはリーマンショックで35万人減少した。その後の東日本大震災と福島第一原発の放射能漏れ事故、さらにはコロナ禍の出入国制限など、ここ十数年の間、外国人の減少を促す事態が相次いだ。
しかし、コロナ禍の入国規制が緩和されると一気に増加に転じた。2023年末の在留外国人数は322万人と過去最高を更新した。年平均20万人の外国人受け入れは、決してオーバーな数字ではない。提言が発表されたとき、研究者の一部には「50年後には1800万人は必要では」との見方もあった。
提言の表題に使われた「日本型移民政策」とは何か。ここも重要な意味を持つ。坂中さんは提言で「人材を『獲る』のではなく『育てる』姿勢を基本とする」と強調している。やみくもに外国人労働者を入国させるのではない、来日前または来日直後に日本語や初歩の技術を習得させ、企業にとって、即戦力に近い形で外国人労働者(移民)を受け入れようというわけだ。
最近、法務省の有識者会議がまとめた技能実習制度の廃止に向けた報告書の中に「育成就労」という言葉が盛り込まれた。技能実習から特定技能へ制度を移行する際には人材の「育成」を促す必要があるというわけだ。新たな在留資格として「育成就労」が検討されているというから、「育成」は外国人労働者受け入れの重要なコンセプトになる可能性がある。
また、具体的な施策として「留学生100万人計画」を掲げた。2008年6月に議連が「日本型移民政策の提言」をまとめたのとほぼ同じ時期に、福田内閣が「留学生30万人計画」を策定している。100万人だと政府計画の3倍余りになるが、坂中さんは「留学を育成型移民政策のかなめと位置付ける」と述べた。
坂中さんは入管局に在任中、在留資格「就学」と「留学」を「留学」に一本化する作業などに関わり、留学生受け入れの重要性をよく理解している。だからこそ、政府の「30万人計画」の3倍以上の留学生を受け入れるよう主張したわけだ。
留学生といえば、その最大の窓口は日本語学校(日本語教育機関)だが、政府は2023年に日本語教育機関認定法を制定、日本語学校を公的な機関として位置づけ、日本語教師に国家資格を与える仕組みを作った。
2019年には留学生が31万人に達し、「30万人計画」を達成したが、コロナ禍にあって、外国人の入国規制でその数が減少し、2022年には23万人にまで落ち込んだ。留学生が100万になるのはいつのことか。
提言に外国人住民基本台帳制度の創設を盛り込んでいるのも慧眼と言える。地方自治体が在留外国人に行政サービスを提供するには、自治体が外国人を「住民」として扱う仕組みが必要だと考えた。それまでは法務省による「外国人登録制度」で国が一括して名簿管理などを行ってきたが、自治体側からの要請もあって、政府は2009年に外国人登録法を廃止するとともに入管法などを改正し、3年後から外国人を自治体の住民基本台帳に掲載するようになった。
「移民基本法」の制定をはじめ、政府による「移民国家宣言」、「移民庁」の創設などは、提言に盛り込んだものの、実現していない。安倍晋三政権時代に首相が「移民の受け入れはしない」と断言したことで、「移民」という言葉を使った制度はすべて見送られている。
ただ、移民庁ではないが、出入国在留管理庁(入管庁)が2019年に法務省の外局として設置された。入管庁は入管局が行ってきた出入国管理だけでなく、多文化共生社会を目指す「外国人の在留管理」も所掌事務とされた。
「日本型移民政策の提言」が公表されてから16年が過ぎた。人口減少は予想通りというより、予想以上のテンポで進んでいる。一方、外国人受け入れの枠組みづくりは、新たな在留資格を創設するなど、様々な形で進められている。そのベースにあるのが「日本型移民政策の提言」ではないか。
余談になるが、外国人材交流推進議員連盟の総会に参加した際、森喜朗元首相と名刺交換した。議員連盟のメンバーは50人余りと記憶しているが、その一人が森さんだった。その森さんから、こんな言葉をかけられた。
「議連として外国人参政権を何とかできんのかね」。外国人参政権といえば、公明党や野党の一部が前向きだったが、自民党には反対論が強く、実現は困難な情勢だった。その自民党の重鎮から外国人参政権の実現に前向きな発言があったことに驚かされた。私は森さんに「外国人受け入れと、外国人参政権はまったく別物ですから、無理ですよ」と答えた。森さんは「移民」より日韓関係が気がかりだったようだ。
(石原進)=つづく