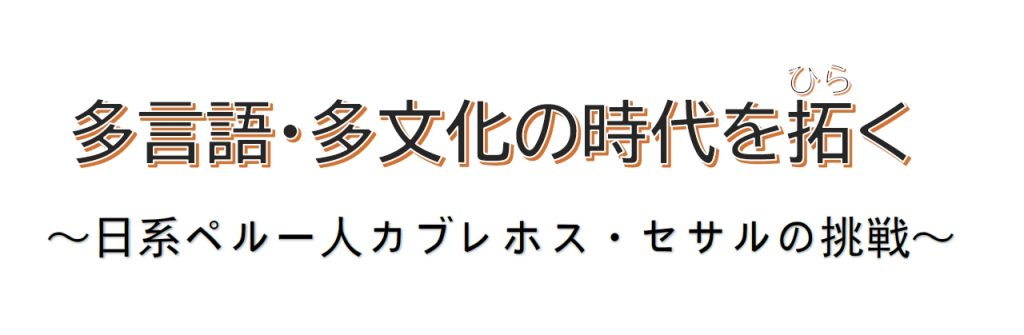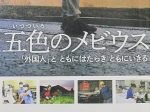セサルの挑戦 第9回 前入管庁長官の佐々木聖子さんにインタビュー

主権国家である以上、国境管理をおろそかにすることはできない。その重責を担うのが出入国在留管理庁(入管庁)だ。佐々木聖子さんは2019年4月に初代長官に就任。22年8月まで同庁のトップとして政府の入管行政と多文化共生の施策をリードしてきた。大任を終えてセサルさんのリクエストの応え、インタビューに応じてくれた。
入管行政は、日本人にはある意味、遠い存在である。海外旅行の際に空港などでパスポートのチェックする入管職員を目のあたりにしても、それ以外の入管業務はほとんど知られていないのではないか。しかし、入管庁が発足して出入国管理に「多文化共生」(在留管理)の施策が加わった。日本人と外国人の「共生社会」を作ろうという、大きなミッションを背負うことになった。
人口減少に伴い在留外国人が急増する中、入管庁の発足は時代の要請だったと思う。そのトップに佐々木さんが就いたのは、人事の「めぐり合わせ」かも知れないが、個人的には、佐々木さんはその大役を担うのだけの力量のある官僚だと見ていた。積み残した課題は多々あるものの、佐々木さんは新たな入管行政の基礎作りをしたと思う。
セサルさんにとっては力の入ったインタビューだった。一方、佐々木さんは「セサルの疑問」に対し飾り気のない口調で答えてくれた。日系人の受け入れの仕組みで来日したセサルさんと、その仕組みを作った入管行政をけん引してきた佐々木さん。「時代」を感じるインタビューである。
(にほんごぷらっと編集長・石原 進)
セサル: 本日お時間いただきありがとうございます。早速ですが、入管行政に携わろうと思われたきっかけを教えてください。
佐々木さん:もともと私は高校の頃から仏像が好きでした。具体的には仏像の研究と保護に関心があって、大学の文学部で美術史を専攻しました。研究は研究で面白かった。職業としては文化財保護をやりたかった。そのために、大学を卒業して文化庁へ行きたかった。国家公務員の一次試験に受かった後、当時は各省庁へ訪問することができたので、私は文化庁を訪問しました。そこで文化財保護をやりたいとお話をしましたが、夢が叶いませんでした。大学に残るか文化財と全く異なる分野を選ぶかを考えていましたが、大蔵省に受かっていた友人から「せっかく国家公務員試験を通っているので、他の省庁も確認してみたら」と助言をいただいた。そこで大学で外国人留学生と接していたし、難民についての本を読んだことがあったので、その分野にも関心があったことから、法務省で外国人を管理している入管という役所を訪問しました。
セサル:留学生と難民は全く別のバックグランドを持つ外国人ですが、どちらにも興味があったということですか。
佐々木さん:その時点では難民について本でしか読んだことがなく頭の片隅に残っていた感じです。
セサル: 法務省以外にも訪問された省庁はありますか。
佐々木さん: 枠が残っていた省庁を人事院から紹介していただいて、いくつかの役所に話を伺いました。経済官庁のような人気官庁は早く枠が埋まっていたので、行けるところを紹介していただいたわけです。
セサル:私のような外国人からすると法務省はどこから見ても堅い、厳しいイメージはあるのですが、なぜあえて法務省を選ばれたのですか。
佐々木さん:基本的にはみんな堅いですよ。(笑)
セサル:確かにそうだと思います。ただ、私であれば最初に法務省という選択はないですね。(笑)
佐々木さん: いくつか理由はあるのですが、私はここでチャレンジしてみたいと思いました。
セサル:法務省に入省してから出入国在留管理業務をご希望されたりしましたか。
佐々木さん:法務省は複数の局に分かれています。入国管理局、民事局、刑事局などがあり、非常に縦割りで、採用も縦割りです。そして私は入管局に採用されました。ほかの省庁では複数の局を経験することが普通で、シニアになっていくとともに専門分野ができていきますが、法務省では基本的に局を行ったり来たりすることはほとんどないのです。但し、武者修行のためにほかの局へ行くことがあります。その武者修行が終わったら親元の局に帰ってきます。
セサル:そうすると佐々木さんはずっと入管局にいたということですか。
佐々木さん:私は入管局に37年いまして、入管を離れたのは2、3回です。これにはメリットとデメリットがあると思っています。メリットとしては専門性が高まるのですが、デメリットとしては世界が狭くす。
セサル:私の調べでは、佐々木さんは1985年4月に法務省に入省され、1994年4月に大阪入国管理局統括審査官になられたと認識しているのですが、この9年間の間の2年間は佐々木さんがおっしゃる武者修行だったということでしょうか。
佐々木さん:そうです。1988年から1990年までの実はこの2年間は研究のために休職をしたのです。
セサル:もう少し具体的にお話をお伺いできますか。
佐々木さん:1985年に入省して1986年に入管窓口に立っていました。そこで在日外国人の対応をしていたのですが、観光ビザで入国するパキスタン人、バングラデッシュ人から、就労したい、日本に残りたいなど、さまざまな声を聞きました。そこで、彼らがなぜ日本を選んでいるのか、人の流れの源流がどうなっているのかが気になったのです。その話を上司に伝えて、自分でアジアを調べたいから休職をさせて欲しいとお願いしたところ、研究休職制度を勧められました。その制度を使って2年間シンガポールにあるアジア研究所に籍をおかせていただきながら、フィールドワークとして各国を訪問しました。
セサル:どういったような国に行かれたのですか。
佐々木さん:インドシナ三国以外はほとんどいっています。
セサル:1980年代後半の日本には中国国籍、朝鮮民族、インドシナ難民の方々が多かったと思うのですが、その2年間の間に日本にいる外国人たちがなぜ在留資格を失っても帰国しないのか、理由がわかりましたでしょうか。勝手な想像ですが、現地行ってみて初めてわかる貧富の差、貧困層の生活、そして一つでもチャンスがあるなら命がけでしがみつく現実を見られたのでしょうか。
佐々木さん:当時日本ではバブルでしたので、出稼ぎのために来日して、仕送りをしたり、母国で家を建てたりすることができると彼らの中でそのような情報が広がり、彼らの目には日本が夢の島のように映っていたため、来日される方が多かったとわかりました。
セサル:佐々木さんが日本に戻った後に考え方は何か変わりましたでしょうか。
佐々木さん:いろんなことを自分の目で見てきたので視野が広がったと思いますし、日本社会が外国人を受け入れることによってどうなっていくのか。それが自分なりに少し具体的に見えるようになったと思います。だから、関心が高まったといえるかもしれないです。
セサル:現在私のような在日外国人が300万人を超えているわけですが、当時日本で在日外国人がこんなに増えると想像ができたのでしょうか。
佐々木さん:増えることはわかっていたので、そんなに驚きはないです。
セサル:私のような日系外国人が1990年の法改正でどんどん来るようになりましたので、在日外国人が非常に増えてきたと認識しているのですが、この点について佐々木さんはどう見えたのでしょうか。
佐々木さん:日系人の話は労働者の受け入れではなく、少なくとも初めは「在留資格の整理」だったと認識しています。要するにそれまでに入れていた外国人の方々の在留資格をどう整えるか。その整理だったと認識しています。日系人というより日本の血を継ぐ方々を受け入れることについての政策は前からある話です。
セサル:私は労働者を受け入れるために作られた在留資格だったと思っていました。
佐々木さん:日系人を受け入れて労働者として採用できるという話は実は群馬県などから始まった話で、どんどん広がったと認識しています。 基本的には在留資格があってからの政策ではなく、政策があって在留資格があるというふうに認識いただければ良いと思います。ただ、その方達に労働者として活躍してもらうというニーズが、日本国内で広まったというのが経緯だと思います。
セサル:非常に興味深いお話ですので、調べようと思えば、そのような情報はどこかに残っていますか。
佐々木さん:入管白書を追っていけば、もしかすると残っているかもしれないです。
セサル:出入国在留管理庁長官になられた時期のことについて、入管局から出入国在留管理庁って結構大きいことだと思っています。そして、初代長官に任命されると非常にプレッシャーがかかるようなことだと思っているのですが、佐々木さんはどのように受け入れられたのですか。
佐々木さん:2018年に特定技能の在留資格がでたのは、外国人労働者の門をより広く開くものと認識していました。今までは技能実習生や日系人労働者の力を借りて進んできていたのですが、きっちりそれらを「日本は外国人の力を借りるのだ」と宣言した状態で在留資格を作りましょうとなったのが、特定技能の在留資格です。そして、この話は入管だけが考えるものではなく、政府全体として考える内容であります。しかも受け入れの話と多文化共生の話が両輪としてあるものです。そのため司令塔が必要になり、出入国在留管理庁が作られました。
セサル:出入国在留管理庁が作られましたが、佐々木さんはどのように長官として選ばれたのでしょうか。
佐々木さん:私は2019年1月に法務省の入国管理局長になっていたのです。同じ年の4月に出入国在留管理庁が作られたため、入管局長だった私がそのまま出入国在留管理庁の長官になりましたので、特に長官として選ばれたという感じではなかったかもしれません。
セサル:そうするとタイミングよくその時期にそのポジションにいられたわけですので、運命的なものだったのかもしれないですね。そこで気になるのですが、入管局の業務に比べると入管庁の業務が増えるように思いますが、業務などはどのように決まっていくものでしょうか。
佐々木さん:入管庁の業務は大きく分けて2つです、1つは在留資格の管理です。2つめは多文化共生、いわゆる外国人の支援業務です。管理業務に関してはもともと入管局時代からの業務を引き継いでいるわけですので、こちらは特に問題はありませんでした。ただし、共生を支援する業務については、入管にとっては新しい分野なので、それまでに支援に関わっていた自治体からの情報を集めたりしました。
セサル:行わなければいけない業務量が大きく増えましたか。
佐々木さん:業務量が増えることに関しては正直、問題はないと思いました。むしろこの二つの業務が繋がって良かったと思いました。逆に反省点があるとすれば、繋げることが遅かった。
セサル:毎年行われている外国人集住都市会議で、いろんな市区町村の首長達が要望を出したりするのですが、外国人集住都市会議は出入国在留管理庁が抱える多文化共生に何らかの影響は与えたりしたことがありますか。
佐々木さん:もちろんです。入国管理局長が初めて参加したのは2019年1月に行われた会議で、私が皆様に、「国としての取組が20年遅れていると思われるかもしれないのですが、始めなければ、始まらないので、始めさせてください」とお伝えしたことがあります。それから、明治大学の山脇(啓造)先生、浜松市鈴木(康友)市長、大田市清水(聖義)市長、大泉町村山(俊明)町長などの方々とコミュニケーションを取りながら、支援方法を考えてきました。
セサル:私自身が最初に参加した外国人集住都市会議は2017年でしたが、そこで初めて、参加された自治体の首長たちが多文化共生について考えていただいていると認識して、多文化共生を支援するための全国1700自治体以上に適用できれる政策がないことを知って少し残念だと思いましたが、それから色々と変わってきた気がしますので、引き続き出入国在留管理庁に多文化共生社会づくりに頑張っていただきたいと心から願っているのですが、佐々木さんが考える理想的な共生社会とはどういうものでしょうか。
佐々木さん:外国人と意識しない普通の隣人と思われるような社会。
セサル:佐々木さん本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
セサルのひと事:
佐々木さんとのインタビューは本当に貴重な経験でした。強い好奇心と自国愛、そして仕事に対する熱意に触れることができ、非常に感銘を受けました。特に、佐々木さんの謙虚さと前向きな姿勢は見習うべきものでした。出入国在留管理庁が立ち上がる過程において、佐々木さんの存在が大きな役割を果たしたことは明白です。2019年の出入国在留管理庁の設立以来、佐々木さんが強調する多文化共生社会の構築において、自治体との連携が鍵となることを改めて認識しました。時間があっという間に過ぎてしまったのは残念ですが、今後も佐々木さんの指導のもと、より良い社会を目指して努力していきたいと思います。
セサルのひと事:
佐々木さんとのインタビューは本当に貴重な経験でした。強い好奇心と自国愛、そして仕事に対する熱意に触れることができ、非常に感銘を受けました。特に、佐々木さんの謙虚さと前向きな姿勢は見習うべきものでした。出入国在留管理庁が立ち上がる過程において、佐々木さんの存在が大きな役割を果たしたことは明白です。2019年の出入国在留管理庁の設立以来、佐々木さんが強調する多文化共生社会の構築において、自治体との連携が鍵となることを改めて認識しました。時間があっという間に過ぎてしまったのは残念ですが、今後も佐々木さんの指導のもと、より良い社会を目指して努力していきたいと思います。