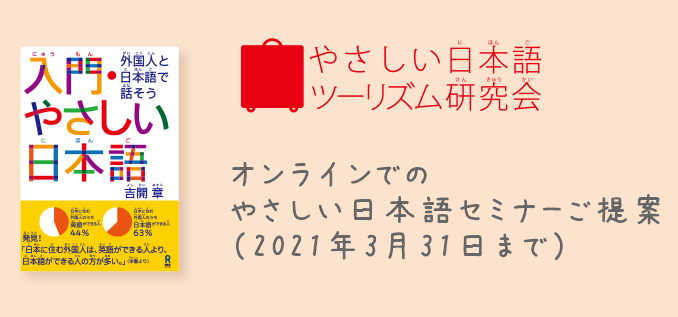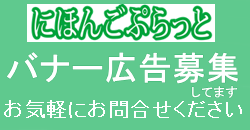外国人は「煮て食おうが焼いて食おうが自由」で共生社会がつくれるのか。

外国人は「煮て食おうが焼いて食おうが自由」で共生社会がつくれるのか。
先日、大手新聞、放送の記者などジャーナリストの勉強会に講師として呼ばれた。テーマは「入管問題」。私はかつて元東京入管局長など入管関係者との親交があった。先の国会で与野党が入管法改正案をめぐり激しい論戦を繰り広げたが、その議論を踏まえて持論を語ってほしいということだった。以下、勉強会を機に改めて「入管問題」について考えてみた。
「外国人は煮て食おうが焼いて食おうが自由」。いま、こんなことを出入国在留管理庁(入管庁)の幹部が言ったら世論に厳しく批判され、更迭されるかもしれない。しかし、半世紀以上前の1965年に「煮て食おうが……」と言ったのは、法務省の入国参事官だった。著書の中でそう言明していた。論拠とされたのは、入管法に盛り込まれた「法務大臣の裁量」だ。
入管法に反する発言でない以上、法務省も「問題発言」だとして入国参事官をとがめることはなかった。1969年の衆院法務委員会で野党に追及された法務大臣は「用いましたことばは、まことに不謹慎きわまるものでございます」と述べながらも、発言の中身を批判することはなかった。
その後、ベトナム戦争の反対運動に加わった米国人の英語教師が在留資格の延長を入管に拒否され、裁判で争った。入管は英語教師が違法とされる政治活動を行ったと判断したようだ。最終的には最高裁は訴えを却下した。司法が「裁量権」にお墨付きを与えたわけだ。
ただ、この「裁量権」には不透明さや、わかりにくさがつきまとう。入管法22条の「永住許可」の要件は「その者の永住が日本国の利益に合すると認めた時にかぎる」と漠然した言い回しだ。同50条の「在留特別許可」でも「法務大臣が特別に許可すべき事情があると認めるとき」に許可される。要するに入管が「総合的判断する」というわけだ。
この「裁量権」こそが、入管行政の本質だと思う。断っておくが、私は入管の裁量権を真っ向から否定するつもりはない。入管行政にとって職務遂行の必要な手立てであることも認識している。とはいえ、「行き過ぎた」裁量権の行使は、ときに外国人支援の団体などの不信感を増幅させる。
2018年の入管法改正以降は、「裁量権の行使」の在り方がより重視されるようになっているのではないか。この年の入管法改正では1条(目的)に「出入国管理」に加えて、日本国内に中長期に滞在する外国人の「在留管理」が加えられた。「在留管理」とはわかりにくい文言だが、ひらたく言えば「外国人支援」である。
また、この入管法改正では、新たな在留資格として「特定技能」も盛り込まれた。これは中小企業の労働力不足を補う施策であり、マスコミ報道では「特定技能」が大きくクローズアップしたが、入管行政を大きく転換させる「在留管理」の意味を詳細に報じるメディアにはお目にかかれなかった。
入管法の目的に「在留管理」が盛り込まれたことに伴い、入管庁には「在留支援課」など新たな部署が設けられた。それまでの出入国の窓口業務や不法滞在者の摘発などから、「共生」の社会づくりが実務として加わることになったからだ。
さらに政府は「外国人の受け入れ・共生のための総合的対応策」を閣議決定した。政府全体として取り組むべき施策を示したわけだ。在留外国人はこれからさらに増加する。彼らと日本人が相互理解を深めながらどのように社会づくりを進めていくのか。入管は重要案件を担うことになった。
そこで何が問題になるのか。そのあたりを分かりやすく説明したい。私たちが「にほんごぷらっと」が詳しく報じているが、名古屋入管局が主導する外国人支援団体のネットワーク化の取り組みがそれだ。「外国人支援団体のネットワーク化」は、「総合的対応策」に盛り込まれた施策だ。
2019年に名古屋入管の藤原浩昭局長(当時)がその施策を愛知、三重、岐阜の外国人支援団体に呼び掛けた結果、「外国人支援・多文化共生ネット」(略称・がいたネット)という連合組織が誕生した。「在留管理」の事業の第一歩である。
藤原局長は入管庁に出向した外務官僚で、外務省時代には外国人課長を経験。「社会統合のための国際ワークショップ」を主催するなどして外国人支援の個人、団体とも付き合いがあった。その一人が三重県のNPO法人愛伝舎の坂本久海子理事長で、「がいたネット」は旧知の間柄の藤原局長と坂本理事長を中心に構築された。
ここで課題として見えたのが、支援団体と入管側との距離感だ。藤原局長の呼びかけで名古屋入管局には20団体の代表らが集まったが、入管主導のネットワークに参加したのは12団体だけだった。参加しなかった団体は入管行政に不信感や警戒感を持っていたとみられる。外国人支援団体のネットワーク化は共生社会をつくるための政府の重要施策であるが、入管当局と支援団体の間に溝があることが図らずも露呈された。
入管にとって「不法就労」や「不法滞在」を摘発は重要なミッションだ。一方、支援団体の中には「不法滞在」を「非正規滞在」ととらえ、重大犯罪だとは見なしていないケースある。米国の不法滞在者は1000万人を超えるが、「不法労働」が経済を活性化させ、経済成長を支えているが現実だ。日本でも「不法就労」が中小企業を支えている面があることは否定できない。
先の通常国会では入管法改正をめぐり与野党が対立したが、焦点となったのは難民申請が3回以上になったら国外への退去強制を可能とする措置。入管側は難民申請を繰り返すことで送還逃れをするケースが多いとし、法改正はそれを阻止するのが目的だ。これに対し支援団側は「帰国させれば命が危ないケースがある」と反発する。
入管当局と支援団体が対立したままで、共生社会が作れるのかどうか。双方が不信感を払しょくするにはどうすればいいのか。ジャーナリスト相手の勉強会では、事態打開の方策の一つとして期待感を込めて提案したのが、政府への「アムネスティの勧め」だ。アムネスティとはわかりやすくいえば恩赦だ。
在留期限が切れたり、在留資格を持たない職種の仕事をしてるけれど、まじめに働き、良き隣人として暮らす外国人がいる。彼らの「不法性」をリセットすることで、わだかまりのない関係ができないか。現時点では入管当局から一蹴されるのは間違いない。だが、「法務大臣の裁量」によって、一挙に数千人に在留特別許可を出せば、事実上のアムネスティだ。
これは高度な政治問題である。知恵をしぼり、時代にマッチした判断をしてほしい。必要なのは、将来を見据えた政治のリーダーシップである。
にほんごぷらっと編集長・石原 進